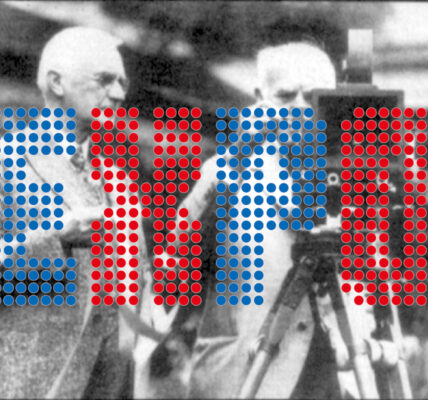【追悼・石井隆】母に捧げるノワール -新たなる石井隆像に向けて-
石井隆の本名が石井秀紀であることは訃報記事で知った。ヒデキ。石井隆のファンがその名から即座に連想するものは石井隆脚本・池田敏春監督の『死霊の罠』に登場する超能力少年ヒデキだろう。映画の冒頭、ヒデキはビデオで録画した深夜番組を見ている。「もう少し前だよ。ああそこ。似てるよね、ママに」彼は番組パーソナリティの名美に亡き母の面影を見る。そして名美をおびき寄せるためにスナッフビデオを撮影して番組へと送る。やがて明らかになるのはヒデキは村木という男の胸部に結合した双生児であり、身体は未成熟で胎児に近いが、その代わりに超能力を発達させていたということだ。超能力を使った残酷なイタズラで名美の気を引こうとするヒデキを村木は必死に抑えようとする。だが、そのためには自分を殺すほかない。ヒデキは村木であり、村木はヒデキであり、生きながらに分離することは不可能だからだ。そしてヒデキ=村木から見た名美もまた、亡き母と分離することはできない・・・。
作家が自作の登場人物に自分の名前をつけることを偶然の一言で済ますのは難しい。大なり小なりそこにはなんらかの狙いがあると想定するのは当然で、それが、その作家がイコンとして用いる姓と直接結びつくのなら尚更だ。では石井隆にとってのヒデキとはどんな存在だろうか。ヒデキは暴力的で、純粋で、残酷で、身勝手で、貧弱で、幼児で、そして母を求めている。ヒデキは村木と石井隆が内に秘めるもう一人の自分であり、村木の中の石井隆でもあるだろう。だとすればこう言うこともできるかもしれない。石井隆が描き続けた名美とは、村木が求める恋人であると同時に、ヒデキが求める母なのだ。
ヒデキが登場する石井隆の映画作品は『死霊の罠』だけではない。監督・脚本作『死んでもいい』において名美(大竹しのぶ)の夫(室田日出男)が土屋英樹という役名。こちらのヒデキには『死霊の罠』の暴力性は感じられないが、共通するのは名美を決して手放そうとしない点だろうか。その結果として命を落とす点も共通するが、しかし、『死んでもいい』が興味深いのはそれよりも、ヒデキを殺して名美と駆け落ちしようとする流れ者の若者・平野マコト(永瀬正敏)の心情を説明する冒頭シーンのように思われる。彼は電車の中で眠りこけている。すると通路を少年が駆けていき、マコトを見守るように向かいの席に座っていた少年の母親がこう言う。「マコちゃんそんなに走ったら、また喘息が…」。
マコトが喘息の持病を持っていることは後に、彼が逗留することになった不動産屋の主人の妻・名美を襲う場面で明らかになる。冒頭シーンの少年と母親がマコトの夢であることはほとんど疑いがない。彼はあてどなく彷徨いながら母を夢見ていた。なぜマコトは名美に惹かれたのか。それは『死霊の罠』のヒデキと同じように、名美に母の面影を見たからではないだろうか。『死んでもいい』の名美を演じたのは大竹しのぶであり、それまで石井隆が劇画と映画で描き続けてきた名美のイメージとは大きく異なる。クールな色気は後景に引き代わりに前景化するのは温かみと包容力だ。石井隆の狙いは明白に思われる。『死んでもいい』の名美は母を象徴する者であり、その夫・ヒデキと疑似的な親子関係を結んだ青年マコトがヒデキを殺して名美を解放しようとする物語は、ギリシア悲劇『オイディプス王』のような父殺しの物語であると同時に、ヒデキ=石井隆の贖罪の物語でもあるだろう。
『黒の天使 Vol.1』が母を喪失した女殺し屋の物語だったこと、『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』が親殺しの物語だったこと、『甘い鞭』が監禁凌辱を受けた少女が母に拒絶される物語であったことなどを思えば、石井隆が母の存在をその作品群の核心に埋め込んでいることは造作もなく理解できるにも関わらず、母としての名美という見方はこれまでにあまりされてこなかったように思う。無論『死んでもいい』の名美がヒデキに対しては妻でありマコトに対しては疑似的な母であり、そのラストシーンではこの世ならざる光の中で二人の男から解放された役割のない女として立ち現れるように、名美は母には還元され得ない多面的な存在ではあるが、『ラブホテル』や『天使のはらわた 赤い教室』といった石井隆が脚本を提供したロマンポルノで描かれたのはもっぱら恋人ないし妻としての名美であり、そうした見方が現在でも批評筋や観客の多くに共有されている(ように見える)中では、名美を母として捉え直すことの意義は小さくない。
おそらく石井隆脚本を映像化してきた様々な監督でさえ名美の母としての側面を見落としてきたのではないだろうか? 数少ない例外は『死霊の罠』の池田敏春であり、陸上の秩序を無効化する広大な海と一体化した怒れる地母神的として女殺し屋を数多く描いてきた池田敏春は、『死霊の罠』や『天使のはらわた 赤い淫画』といった作品で弱々しく孤独に傷ついた村木を留保付きでも受け入れこそすれ恋人としての顔は見せない母として名美を捉えていたように見える。石井隆が名美の母としての側面を重視していたとすれば、石井隆が池田敏春の監督作に数多く脚本を提供したのも頷ける。二人の映画作家の海の表象――石井隆にとっての海は人間を拒絶する都市の迷宮の行き止まりであり、池田敏春にとっての海は人間が汚らしい地上を捨てていつか帰るべき場所――の違いを見れば、石井隆は池田敏春のロマン主義に憧憬を持っていたかもしれない。ロマン主義こそ母性の揺籃なのだから。
しかし石井隆は池田敏春のようには母を描かなかった。むしろ逆に、ゼロ年代以降は母の幻像を徹底して打ち砕く道を選んだ。打ち砕かれるのは母の幻像だけではない。妻の幻像、恋人の幻像、娘の幻像、父の幻像、夫の幻像、息子の幻像、そして村木の幻像と名美の幻像、あるいは愛の幻像、もしくは石井隆の幻像もまた容赦なく打ち砕かれることになる。『フリーズ・ミー』ではレイプ被害者の会社員(井上晴美)が婚約者から見捨てられ、加害者たちをたった一人で殺害した後、彼女をその境遇に追い込んだ婚約者を自らの手で殺す。『花と蛇』では死を目前に控えて母胎回帰を夢見る老ヤクザ(石橋蓮司)がダンサー(杉本彩)を監禁・調教するが、SMではなく老ヤクザの求める母の役割を果たした後の、老ヤクザに全てを奪われたダンサーの魂の彷徨がこの映画のクライマックスになる。
明らかに過小評価されているその続編『花と蛇2 パリ/静子』にはダンサーの妻(杉本彩)との関係が破綻した美術評論家の夫(宍戸錠)が女装して妻のSMを覗き見る、というシーンがある。これは何も復讐心やスケベ心からの行為ではない。彼は妻との関係修復を切望しているのだが、それを歪んだ形でしか実行することができないのだ。女装は妻と同化することであり、その眼差しが捉える妻の被虐は、彼自身の被虐・自罰行為となる。『人が人を愛することのどうしようもなさ』ではセルフパロディ的な劇中劇に縛りつけられ、映画監督や観客の持つ女優としてのイメージと自己イメージが乖離し、現実と虚構の狭間を彷徨う名美の苦悩が描かれる。石井隆のフィルモグラフィーの中で最もラディカルなこの映画を最後に、石井隆は名美と村木の物語を撮っていない。『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』の村木は村木の名を捨て紅次郎を名乗っている。そしてそこで描かれるのは父殺しと、家族神話の転覆と、優しく包み込む母の幻像の解体である。
これらの脱構築的な作品群を石井隆の変節を表すものと見る向きもあるだろうが、『GONIN』が男として失敗したと思い込む男たちが男らしさを取り戻そうと暴走する物語だったように、『ヌードの夜』が妻でも母でもなく誰のものでもない女であろうとして苦闘する名美の物語だったように、『天使のはらわた 赤い眩暈』が子供のように弱々しく名美に救いを求める村木の物語だったように、キャリア初期から石井隆は男らしさや女らしさの解体を試みてきた。『死んでもいい』に効果的に挿入されるちあきなおみの絶唱「黄昏のビギン」は石井隆が新宿二丁目のゲイバーで教わったものだ。
こうした「らしさ」の解体は記号化し硬直した人物に自由に広がっていく生を吹き込むだろう。『GONIN2』ではそれまでの石井隆作品で名美を演じてきた大竹しのぶ、夏川結衣、余貴美子に加えて後に『人が人を愛することのどうしようもなさ』で名美を演じる喜多嶋舞が一堂に会し、母や妻や殺し屋といった単一のペルソナには決して収まらない名美の多面性が確認できる。『GONINサーガ』の登場人物たちには今までの石井隆映画にはない若々しさと表情がある。彼ら彼女らにとって親は○○の子、というペルソナを自分に張り付ける抑圧者に他ならず、その戦いは親と親世代の軛を断ち切り自分らしく生きるための戦いなのだ。「らしさ」の解体とは、人物をその過去から解放することに他ならない。そして石井隆が生涯描き続けたのは過去に囚われ、過去に抵抗する男女だった。
だとすれば、こう言えるかもしれない。石井隆が母に拘り続けたのは、決して叶わなかったかもしれない、石井隆が奪ってしまったかもしれない(母の生を奪わぬ子など存在するだろうか?)、その自由な生を、たとえ映画の中ででも母に与えたかったから。石井隆のノワールは、母に捧げる鎮魂歌であり、その生を祝福する賛美歌である。そのように石井隆の像を解体することで、私もまた今や動かぬ石井隆に生を吹き込みたいと思う。