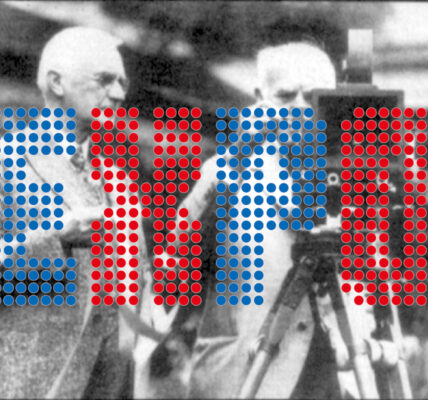【ミニミニ特集】ジメジメ…ジトジト…そんな梅雨に見たい映画11選!
気がつけばもう6月、梅雨の時期でございます。みなさん梅雨をどうお思いでしょうか。雨ってなんか詩情があっていいなぁというポエムな人もいれば明日も雨かよ仕事行くのダルいわ~という人もいるだろうと思いますが・・・ここでむしろあえて逆に提案です!外に出るのが億劫な梅雨どきこそ、家で映画三昧のできる映画好きにとって理想の季節!ということで梅雨を逆手にとってみなさん映画を見まくってみてはいかがでしょうか!
そんなわけで梅雨に見たい映画を11本選んでみました!ホラーありSFあり人情ありのまるで統一感のない11本をどうぞ!たぶんだいたいAmazonとかで配信してるやつだと思います!
シェルブールの雨傘(1964)
梅雨ってジメジメしていてなんだか嫌ですよねぇ~。そんな気分が落ち込みがちな梅雨を楽しく味わう作品と言えばコレ!フランスのミュージカル映画『シェルブールの雨傘』だ!
石畳を彩るカラフルな傘たちを真上から映したご機嫌なショットで始まる本作。そこからいよいよストーリーが始まるのだけれど、登場人物たちが端役も含めて全員歌うようにセリフを喋っている!なんとこの映画では日常のシーンとミュージカルシーンが分かれておらず、最初から最後までミュージカルシーンなのだ!最初はその構成に違和感を覚えるかもしれないけれど、カラフルなセットと日々の生活に優しく溶け込むメロディになんともうっとりとさせられて、知らないうちに港町シェルブールの世界に入り込んでいってしまう。
作品の冒頭では若い男女が結婚を誓い合うほどにお互いを愛し合っていたにも関わらず、男がアルジェリア戦争に徴兵された事により長い間離れ離れになってしまうという、青春の甘さと苦さを描いたとても大人の作品となっている。特に終盤で二人がある場所で再会するシーンが素晴らしい。ハリウッド映画だったらクライマックスに向けて大胆に盛り上げる所を、この映画ではサラッと終わらせる所がなんともリアル。大人になるって事は理想と現実に引き裂かれながらも、淡々と日常を生きる事なんだよなとしみじみと感じさせられる。
カラフルでキュートな世界に込められた、大人のビターなストーリー。雨の日にしみじみと味わいたい一作。カトリーヌ・ドヌーヴもフレッシュだ!
(ぺんじん)
赤い影(1973)
精神を逆撫でするような、意図不明、意味不明のカットバックが時々映される異常に不安で不穏な雰囲気の中で、真っ赤なレインコート姿の少女が雨の中で池の周りで遊んでいる。そして案の定、悲劇は起こり、少女は池に落ちて溺死してしまう。ドナルド・サザーランド演じる父親が、その赤いレインコート姿の少女を池から助け出すところが何度も執拗に映される。「赤い影」のタイトルのせいもあり、この赤いレイコートの少女の姿が焼き付いた状態でこの映画は進んでいく。非常に意地悪な映画だ。
その赤い影がどうなるのかぜひ確かめていただきたいが、このようにレインコートを不穏に見せる映画というのはとても多い。この映画の影響がとにかく大きかったらしい。黄色いレインコート姿の殺人鬼が現れる『アリス・スウィート・アリス』は監督が『赤い影』の影響を公言している。クローネンバーグの『ブルード/怒りのメタファー』はレインコートでは無いが赤や青のスノージャケットを着た子どもが印象的に現れるが、これに非常によく似ている。また日本のホラー映画『仄暗い水の底から』でも黄色いレインコートが印象的だ。スティーブン・キング『IT』でもまた黄色いレインコートが非常に怖いシーン印象的に使われる。ダリオ・アルジェントの『フェノミナ』ではレインコートは着ていないがほぼ同じようなシーンが有る。『赤い影』に影響をうけた、また引用した映画や映画監督は非常に多い。映画の中のレインコートを追いかけながら、梅雨の景色をぼんやり眺めてみるのも中々楽しいかもしれない。
(左腕)
仄暗い水の底から(2002)
『事故物件 恐い間取り』や『“それ”がいる森』によって今やすっかりC級監督みたいな扱いになってしまった中田秀夫だが、90年代~00年代にかけては『女優霊』『リング』とJホラーの金字塔を立て続けに放ったJホラー中興の祖、そしてこの2002年の『仄暗い水の底から』はそんな時代の中田秀夫が原作は『リング』の鈴木光司、脚本は『ほんとにあった!呪いのビデオ』や『残穢』の中村義洋、音楽には押井守作品などで知られる川井憲次を迎えて撮り上げた、Jホラーのひとつの到達点というべき作品だ。
といっても実は大して怖くない。怖いのは最後に出てくるオバケの顔ぐらいで、それまでは梅雨時で湿気がものすごい老朽化した団地の放つなんともイヤ~な雰囲気で見せる、怖いというよりは気味が悪いという表現の方がしっくりくる映画だろう。けれどもこれがよくできているのですよ。元夫との親権争いの中で大きなプレッシャーを感じている主人公のシングルマザー(黒木瞳)の不安が生み出した幻影なのか、それとも本当にオバケの仕業なのかわからない、日常の中のちょっとした気味の悪い出来事の丁寧な積み重ねが、昭和のマンモス団地の陰気でカビ臭い空気を増幅して、ここならオバケが出てもおかしくないと強く思わせる。人情や愛情が執着と怨念に反転する物語は古典的な怪談話のそれ。Jホラーの手法を用いてすっかり廃れた怪談話(実録怪談や都市伝説にあらず)を見事現代に再生した、なにやら怪談映画の新たなる古典の風格さえ漂う一本。
(さわだきんた)
ブレードランナー(1982)
梅雨に見たい映画特集ということだが、雨というのは一般的にはまぁマイナスイメージが強いものであろう。休日にお出かけするってときに雨が降ってたらガッカリはしてもワクワクする人はあまりいないと思う。そしてこの『ブレードランナー』という映画は雨が持つそういったイメージを最大限に利用した映画であるのだ。
『ブレードランナー』といえば言うまでもなくサイバーパンクというジャンルの中でも極めて重要なポジションの作品で、こと映像面においては最重要というか、この作品がサイバーパンクというジャンルから想起しうる全ての視覚イメージの根源にあると言っても過言ではない映画である。サイバーパンクという物語ジャンルはそこにある“パンク”というワードからも分かるように夢いっぱいで明るく希望に満ちた未来へといったようなビジョンに異を唱える作風のものが多い。逆転不可なほど貧富の差が大きくなって持たざる者はとことん下層の階級で生きていくしかなく、暗く陰鬱なマイナスイメージな世界が多く描かれる。
そんな世界観の中で原作にはない要素であるにも関わらずサイバーパンクというジャンルの中で定着した『ブレードランナー』における雨とは何だったのか。それは匂いのようなものではないかと思う。目には見えなくてあるのかないのかよく分からないが、生々しくて強烈な印象を与えるもの。ネオンに彩られたメタリックな世界に実在性を与えることができるのは匂いで、それはきっと雨上がりのアスファルトから漂ってくるようなあの感じなのではないだろうか。特に雨に濡れた路面というのはストーリー以上に本作を雄弁に語っている気さえする。物語後半で人間よりも人間らしいロイ・バッティの存在が人間性の鏡面のように描かれるように、ギラギラしたネオンの光が反射する濡れた地面からは雨という単なるマイナスなイメージだけではなく、肌や粘膜を通じて感じる匂いや湿度といった生きている実感があふれ出しているのである。
ぜひ雨音が聞こえるような日にお家で見ていただきたいですね。それは劇場で観るのとはまた違う印象を与えてくれるだろう。見終えた頃に雨が止むタイミングならなおよしです。雨だってやがて止むし、雨の中で流した涙も乾く、という風に…。
(ヨーク)
ヒッチャー(1986)
大雨の中、ヒッチハイクをしていた男を乗せてしまったことで悪夢のドライブが始まる。荒野のど真ん中で、薄暗くて青っぽい闇の中、ぬらりと現れ、乗り込んでくる男はルドガー・ハウアー。その水に濡れた姿が妙に色っぽい。男は車を運転しているC・トーマス・ハウエル演じる青年と会話を始める。だが微妙に話が噛み合わない。そして次第に男は恐ろしい本性を見せ始める。この冒頭からして異常に緊張感に満ちているスリラー映画の傑作。そこから始まるハイウェイを舞台にした追いかけっこ、だがこの映画は魅力はそれだけではない。次第にその追う、追われるの関係の中で、青年と男の間で奇妙な絆が生まれていく。男はどこか青年に殺されることをずっと望んでいるようであり、また青年も男を殺すことに執着していく。
映画の序盤と終盤ではこの青年の顔つきが全く違う。この二人の男が相対した時の妙なエロス。男同士の悲恋の映画としての雰囲気が、この映画を荒野の乾いたアクション・スリラー映画ではなく、湿度有る怪談のような物にしている。 冒頭しか雨の降るシーンはなく、後はただ乾燥した荒野の景色が続くが、男たちは汗でぬらぬらと湿っている。ルドガー・ハウアーの異常な色っぽさ。そしてそのC・トーマス・ライリーに向ける視線。そして何やら一方の男に、一方の唾液がつくようなシーンが二箇所もあり、ただ事ではない湿った雰囲気が全編を支配している。そんな映画だ。
(左腕)
シー・オブ・ザ・デッド(2013)
網漁でデブ人魚ゾンビ(巨乳)を釣り上げるという前代未聞の導入から始まる今作は、とある村にゾンビが襲い掛かるという設定“だけは”オーソドックスなブラジル製ゾンビ映画だ。今回これを紹介したかった理由は何といってもこの映画「湿度」がヤバいから!今作、とにかくやたらとグチャドロしたゾンビが出まくる。メイクはかなり力が入っており皮膚が爛れてドロドロなゾンビが目白押しだし、血糊の量も半端じゃない。心なしか血糊の粘度も妙に高めに見えドロドロ感をUPさせている。
全体的にキャラクターどものテンションが異常であり、漁師や政治家や黒魔術青年やシリアルキラー(!?)を始めとした、やたらとエキセントリックなキャラたちの群像劇が全く上手くまとまらず炸裂し続けるのも特徴である。ハゲのドラァグクイーンがゾンビの群れに向かってガトリング銃をぶっ放すなどといった映画史上最初で最後と思われるような画面が連発し、衝撃のラストを含め、面白いかはともかく一生に一度の「何か」を目撃してる感は味わえるはずだ。
・・・と言いつつもじつは1時間くらいほぼゾンビが出ない映画でもあり、そこではただただゆっくりとした時間が流れる。一見欠点のように思えるがしかしこれがなかなか独特の空気感があり割と面白いのである!ダル日常もの×湿度、この両面からジメジメした梅雨にオススメなゾンビ映画と言えるだろう。
(ハカタ)
パリ、テキサス(1984)
6月になるとやけに雨が降る日が多いなぁ、ジメジメしているのイヤだなぁ、コワいなぁ…と思っている人にオススメな映画はコレ!テキサスのカラッとした荒野から始まる『パリ、テキサス』だっ!映画を観る前はなんとなくパリ・テキサス間でおじさんと美女が電話している映画だと思っていたけど、実際はショックで茫然自失となったおじさんが、かつて自分で購入した「テキサス州のパリ」という謎の土地を求めて荒野をさまよっている映画だったのだ!フランスのパリ全然関係ない!
そのため舞台はアメリカ南部のテキサス、そしておじさんの身柄を引き取りに来た弟の住むロサンゼルスという湿度の低いカラッとした場所に限定される。監督がドイツ人のヴィム・ヴェンダースだから結構オシャレな映画かと思いきや、意外と人情味のあるロードムービーに仕上がっている。メインテーマは壊れてしまった家族とその愛情についてで、どこか倉本聰的な雰囲気のストーリーがじんわりと心に沁みてくる。
近いようで遠い家族の距離。マジックミラー越しにハリー・ディーン・スタントンとナスターシャ・キンスキーが会話するという演出が二人の距離感を表していて素晴らしい。偶然撮れたというマジックアワーの映像の美しさも心に残る。遠く離れてしまった家族に思いをはせる…引きこもりがちな梅雨の時期にピッタリの映画だ!
(ぺんじん)
クロール -凶暴領域-(2019)
雨はいつでも映画の中で世界を塗り替えてしまうが、文字通り世界が変わって崩壊してしまう災害映画。大雨や嵐ですべてが吹き飛ばされ、更地となり、そこに人間の再生のドラマがある。世界を流す大雨。けど、そこにワニがいたらどうなってしまうのか…大雨だけでも大変なのに、水浸しとなった世界はワニ達のホームグラウンド。この映画は、災害あり、親子のドラマあり、水泳にかける熱血スポ根あり、そしてワニが人を食べまくる動物パニックあり。その全てを、ほぼ一軒の家の周りだけで完結させ、見せきってしまう恐るべきワニ映画屈指の一本だ。いや動物パニック映画の中でも指折りの作品にさえ思える。
この「一軒の家だけ」というのはスケール的に狭く思いB級的に感じるかもしれないが、この「家」という舞台立てが親子のドラマと密接に関係している、また家の空間使いも素晴らしく、下から上に移動していくお話も、親子の這い上がりと再生を感じさせるものである。登場人物は最低限ではあるが、キルカウントが少なく興ざめということもない。次々と投入される食べられ要員、しかも皆しっかりと食べられるのでかゆいところに手が届く。感動したのはワニの必殺技といっても過言ではない「デスロール」(獲物に噛み付いた後に身体を回転させ食いちぎるワニの修正)が満を持して描かれるシーンがまさかの感動的なシーンとしてカタルシスをもたらすところだ。大雨の日に見ると臨場感も十分。梅雨の時期や台風の時期には毎年見たくなる映画だ。
(左腕)
羅生門(1950)
二人の男が雨宿りのために入った羅生門にはもう一人の雨宿り客がいた。彼が退屈しのぎにと語り出したのは「人は誰しも自分の都合のいいようにウソをつく」というなんだか気の滅入るような事件の話だった・・・という物語の枠組みだけは一応芥川龍之介の代表作『羅生門』から取られているが、本題は同じ芥川の『藪の中』。監督の黒澤明の戦中の作『虎の尾を踏む男達』の発展系にあたる実験作で、真相不明の事件を当事者三人の証言と回想のみで、能楽のスタイルを借りて描いた異色のミステリーだ。
『閉ざされた森』や『怪物』などといった一つの出来事を複数の人物の視点から物語り、その食い違いが謎を生むミステリー映画は俗に「羅生門スタイル」と呼ばれる。それら後発の作品と『羅生門』が異なるのは結局真相はよくわからないままという点。雨も降っているしモヤモヤすることこの上ないが、今でも語り草となっているギラつく太陽を捉えたショット(※フィルムが焼けるので御法度とされていた)は力強く、なにがなんだかよくわからないが最後には雨もあがって二人の雨宿り人も捨て子の育児という希望を見出すので、あんがい後味は悪くない。戦争の記憶の未だ色褪せぬ1950年の作。モヤモヤを抱えつつも前に進んでいこうとする雨宿り人の姿には、戦後日本人の気分が反映されているのかもしれない。
(さわだきんた)
殺人の追憶(2003)
大学時代、梅雨の坂を数人で下校する中、サークルのマドンナ的な同級生に「梅雨の映画ってある?」と聞かれたのを思い出した。その場にいた映画好きの後輩は、「梅雨じゃないんですけど、『パパの木』がおすすめですよ」と、その後延々とパパの木の話をしていた。オタクが嫌われるのは、こういうとこだと思う。それがいかに素晴らしい作品でも、相手の話に合わせてチューニングする力が必要だ。彼はその後『マニアック』の頭皮を剥ぐシーンをオススメしていたが、彼女がその映画を見るわけがないのだ。彼はその後サークルで居場所を失い、私自身も別件で強く当たってしまい疎遠になってしまった。彼のその後は誰も知らない。
映画好きが集まってこその映研なのに、映画が好きな奴なんて全くおらず、クラスの延長線上的な世界ではキモいオタクは排除されてしまう。それでは、彼の居場所はどこにあるというのだろう。しかし先述の話は何も女性に対してだけではない。社会で生きていく上で、キモいオタクを受け入れてくれる人などいないのだ。だから我々こそ、コミュニケーションを勉強し、強く生きていかねばならない。その後Filmarksで彼らしき人物を発見し文字数
(二階堂 方舟)
タレンタイム 優しい歌(2009)
雨期の映画だったかどうかは定かではないのだが記憶の中のこの映画の風景はちょっと空がどんよりしている。タレンタイムというのはマレーシアでは一般的なものなのかそれともこの映画の中の高校の独自制度なのかは知らないが、生徒一人一人が歌や踊りなんかを披露してタレントとなる、日本で言うところの文化祭、もしくはアメリカで言うところのプロムのようなものらしい。
映画はこのタレンタイムの期間中に巻き起こる生徒やその周辺の大人たちの様々な心の揺れや小さな衝突、和解や友愛を群像劇のスタイルで描くもので、マレーシアの俊英監督ヤスミン・アフマドの遺作。多民族国家マレーシアの現実をリアリズム的に抉りつつもあくまでも温かな眼差しは手放さず、大きな悩みから小さな失敗まで、主役から脇役まで、すべての出来事や登場人物を平等に、ほんのりとユーモアを交えて慈しむように捉えているのが素晴らしい。
人生は時に残酷で時にバカバカしくて時には冷たいが、ともあれそれでも灰色の空の下で人生は続く。この映画を見た後には憂鬱な外の雨音も、どこかやさしい音色に変わっているのではないだろうか。
(さわだきんた)