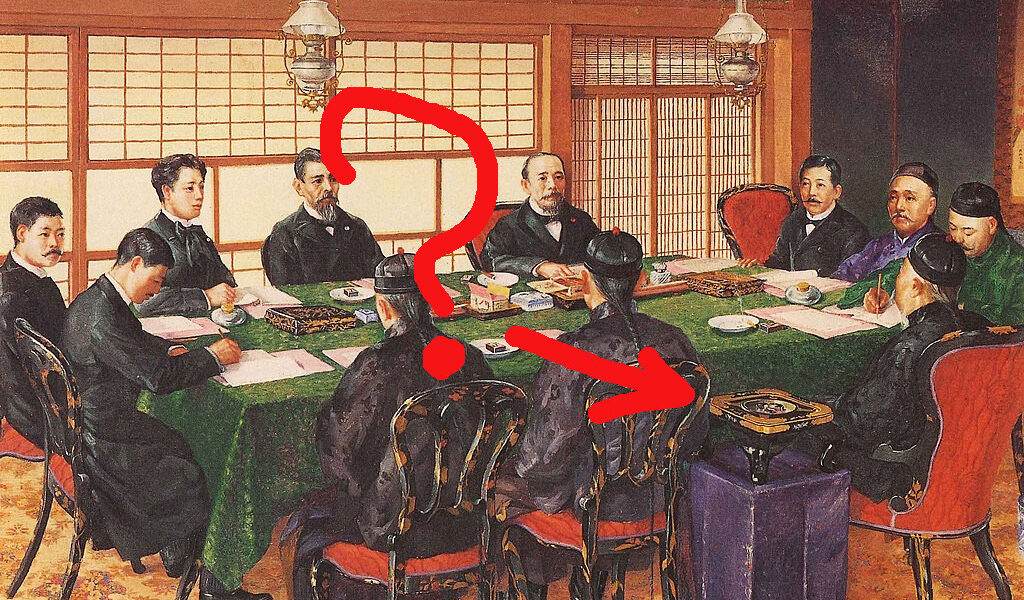【あの映画のあれ】あれ10 『宝島』(2025)で描かれる「アメリカ統治下の沖縄」
現在公開中の映画『宝島』は戦後アメリカ統治下の沖縄を舞台にした上映時間191分にも及ぶ大作大河ドラマ。その時代背景は映画を見ていればわかるものの、教科書ではないので詳細が説明されることなく、なんだかよくわからんかったという人も結構いるんじゃないでしょうか。このコーナーはいろんな映画に出てくるがよくは知らないアレについて理解を深めるトリビアコーナー。ということで今回は「アメリカ統治下の沖縄」をネットで調べてざっくりとまとめてみましょう。
さて、映画は1952年から始まります。劇中では米軍嘉手納基地に侵入して貧しい住民のために物資を調達してくる戦果アゲヤーと呼ばれる若者たちのリーダーが失踪する事件が起こり、ここから元戦果アゲヤーの若者たちの波瀾万丈の二十年間が始まるわけですが、1952年はサンフランシスコ平和条約が発効し、それまでアメリカ占領下にあった日本が主権を回復した年。ところがこのサンフランシスコ平和条約、沖縄は対象に含まれておらず、それから沖縄返還が実現する1972年まで、日本の中で沖縄だけが依然としてアメリカによる占領状態が続くことになったのでした。
アメリカ占領の問題は住民の自治権が限定的にしか認められなかったこと。沖縄の人が運営する琉球政府は存在したものの、これはあくまでも琉球列島米国民政府(USCAR)の下部組織。琉球政府の決定は上部組織であるUSCARが破棄する権限を持っていたため、沖縄に住んでいる人が求める法律などが自由に作れなかったわけです。加えて1952年、現在の日米地位協定の前身となる日米行政協定が制定されました。これは在日米軍の地位を保障するための協定で、その中には米兵および軍属が基地外で犯罪を起こした場合、身柄はアメリカ側に引き渡すとする条項が含まれていたため、犯罪を起こした米軍関係者を日本の法律で裁くことができないという問題が出てくることに。これは現在でも度々ニュースになったりしますね。
映画の主な舞台は沖縄本島中央部にあるコザの街。東アジア最大の規模を誇る米軍嘉手納基地の周辺に広がるコザは一方で米兵のもたらすお金や文化によって県内随一の繁華街へと成長しつつ、一方で先に述べたような沖縄住民と米軍関係者の不平等な関係によって様々な事件が起こった(そしてその犯人を警察が捕まえたり裁判にかけたりできなかった)、アメリカ占領下の沖縄の抱えた矛盾の凝縮された場所。ちなみにこのコザで1970年、米兵による住民のひき逃げ事件に端を発して巻き起こったのがコザ暴動で、映画の中でもコザ暴動は大きな見所になっています。
太平洋戦争の際に唯一の地上戦が行われた沖縄は、いわば死に体の大日本帝国の人間の盾にさせられたわけですが、戦後においても日本政府は日本本土の主権回復を優先して沖縄の自治権を認めないサンフランシスコ平和条約を受諾したわけで、沖縄は日本本土の政府から二度に渡って見捨てられたことになります。にもかかわらず映画にも出てくるように沖縄で本土復帰運動が1960年代に活性化したのは、小学校に米軍軍用機が墜落し児童十数人が死亡した1959年の宮森小学校米軍機墜落事件や、1969年の嘉手納基地毒ガス漏出事故(これによって嘉手納基地内に毒ガスが貯蔵されていることが明らかになった)、そのほか大小様々な暴力事件などの被害がアメリカ統治下で生じていたためで、戦中戦後にかけての沖縄は日本からもアメリカからも差別され、いいように利用された土地といえるかもしれません。
と、こんな背景事情を頭に入れて『宝島』を見れば、より楽しめること請け合いじゃないでしょーか。