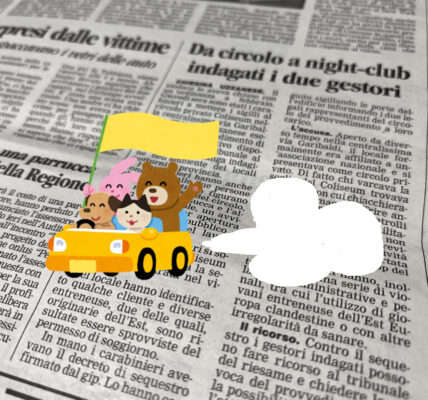【放言映画紹介 ウチだって社会派だぜ!!】第6回後編 ポリコレ議論に先人あり!黒人エルフ事件×『ウィズ』
前編はこちら
鳴り物入りで公開された大作『ウィズ』であったが、興行収入は惨敗であった。なぜ失敗作になってしまったのだろうか?
元々『ウィズ』はモータウン・プロダクション(レコード会社モータウンの映画部門)が手がける同名舞台版の映画化企画であった。予定では『サタデー・ナイト・フィーバー』(77)でお馴染みのジョン・バダムが監督し、舞台版でドロシーを演じた新人女優ステファニー・ミルズが主演を務めるはずだった。おそらくルメット版『ウィズ』に比べ、もっと小規模で舞台版に忠実な映画ができるはずだったに違いない。
そう・・・ダイアナ・ロスが来るまでは。
黒人女性歌手グループ「ザ・スープリームス」のメインボーカルとしてデビューし、数々のヒット曲を世に放ったダイアナ・ロスはまさにR&Bの女王とも言うべき超偉大な大スターである。当時彼女はモータウン制作『ビリー・ホリデイ物語 奇妙な果実』(72)で女優業に進出し、初主演でなんとアカデミー主演女優賞にノミネートされる快挙を達成している。私生活ではモータウン社長ベリー・ゴーディ(既婚者)との間に一女を儲け、まさに公私ともに絶好調だった時期だ。
さて、『ウィズ』の企画を嗅ぎつけたダイアナは、どうしてもドロシー役を演じたいとベリー・ゴーディに直訴する。しかも自分でユニバーサルとの協力も取り付けてしまったというのだから恐ろしい。結果、周囲の反対を押しきって役を強奪してしまった。主役交代を知ったジョン・バダムは降板、予算内に大作を完成できる人物として全く畑違いのシドニー・ルメットに監督が回ってきたといういきさつである。
ダイアナの暴走は止まらない。当然、脚本にも口を出す。当時彼女と脚本担当のジョエル・シュマッカーは「エスト」という自己啓発セミナーにハマっていた。そのせいか『ウィズ』はエスト思想から影響されたと思しきセリフや歌詞であふれている。子供だましのストーリーに取ってつけたような自己啓発の文句が並ぶのだから、酷評されるのも当然である。本作のプロデューサーを務め、後に映画監督として有名になったロブ・コーエンは『俺はこの脚本がマジで嫌いだった。ダイアナとの話し合いも大変だったし。彼女はエストで学んだことをこの映画に注ぎこもうとしていたんだよ。』と語っている。
前編で『ウィズ』を早すぎた『力の指輪』とご紹介したが、どっちかというと早すぎた『えんとつ街のプペル』かもしれない。映画史は意外なところで繋がっているのである・・・。(ということにしといてください)

ダイアナは美人で演技力があって歌もうまいが・・・協調性がない点が映画俳優としては致命的だった。その結果が『ウィズ』である。(マーヴィン・ゲイ曰く「言っとっけど、ダイアナはスターになる前からあーゆう性格だったよ」)彼女が満を持してミュージカル映画に挑戦するというのであれば、『ニューヨーク・ニューヨーク』(77)だとか『キャバレー』(72)ようなビターでシニカルな大人向けの作品を用意すべきであった。それこそ当初の予定通り、『サタデー・ナイト・フィーバー』で労働者階級の苦い青春を描いたジョン・バダムであれば・・・!と思わずにはいられない。
さて、ダイアナがハマった自己啓発セミナー「エスト」とやらについて少しご紹介しよう。正式名称は「エアハード・セミナーズ・トレーニング」である。トレーニング参加者は飲まず食わずの合宿で、仲間と一緒に自己を見つめ、語り合い、心を開放し、ありのままの自分を肯定をする・・・らしい。(カリキュラムを読んでみたがウチの英語力では正直抽象的すぎてよくわかりませんでした。)
特徴的なのはセレブとの繋がりで、芸能界ではジョアン・ウッドワードやロイ・シャイダー、ジョン・デンバーなどが彼の顧客だった。しかしながらこのエアハード、かなりうさん臭い人物で、児童虐待や脱税疑惑で何度も訴えられている。(全然関係ないけど、サイエントロジー創設者ロン・ハバードは「エスト」がサイエントロジーのパクリだとして敵対視していたらしい。サイエントロジー信者を合宿に潜入させ、トレーニングを妨害するなど姑息な工作を行っていたそうだ。何というかその場に居合わせたらいたたまれないだろうな。)
さて、ここまで『ウィズ』のダメな点を散々書いてきたが、最後に一つ見所をご紹介しよう。それは善き魔女グリンダを演じたレナ・ホーンである。彼女はこれが最後の映画出演となった。
1917年、白人の父と黒人の母の間に生まれたレナは幼い頃から苦労の連続だった。まず彼女が3歳の時に父親が失踪、母は女手一人で何とか娘を育て上げた。大人になった彼女は生活費を稼ぐためにジャズ歌手としてデビューし、実力が認められ映画界に進出することとなる。経歴的にはダイアナ・ロスの大先輩であると言えよう。
美貌と歌唱力で一躍スターになったレナであったが、活躍の機会に恵まれたとは言い難い。1940年代のアメリカはバスもトイレもレストランも学校も黒人と白人で別だった時代である。いくら才能があっても黒人女優に大作の主演など回ってくるはずがなく、主演に予定されていたミュージカル映画『ショー・ボート』(51)でも、人種を理由にエヴァ・ガードナーに交代させられている。
『ザッツ・エンタテインメント PART3』(94)で当時の思い出を本人が語っている。「歌ったらすぐ立ち去るような役ばかりで、演技させてもらえなかったの。」「エヴァとは友人だったけど、役を降ろされたのは本当にショックだった。」「やっと掴んだ役も入浴シーンが原因で出番をカットされてしまった。」全く、ひどい話である。
NYハーレムで生きる性的マイノリティの若者を映したドキュメンタリー映画『パリ、夜は眠らない』(90)の中でトランスジェンダーの黒人女性がこう話す場面がある。「アタシは昔、マリリン・モンローになりたかった。でも本当はレナ・ホーンを目指すべきだったのにね。でも、レナ・ホーンになりたい子なんて誰もいなかった・・・。」
『ウィズ』のラスト、レナ・ホーンが『Believe In Yourself』を歌うシーンは不遇の時代を経てついに本領発揮といた輝きに満ちている。歌詞こそエストの決まり文句だらけなのだが、空虚な白人男のスローガンではなく実感がこもった言葉のように聞こえるのだ。この入魂の歌唱を聞くだけでも『ウィズ』を鑑賞する意義はあるだろう。前編で「仏作って魂入れずというような空虚な大作」と書いたが、魂は確かにあったと思う!ダイアナ・ロスの奮闘(?)とレナ・ホーンの輝きという魂が!
ただし、魂は仏に入らずOver the Rainbow・・・虹のかなたに飛んでいってしまったが・・・以上!